|
葉 【Leaf】
|
|
|
概要 植物の茎や枝につき、光合成と蒸散を主な役割とする器官。 |
2017/09/15(作成)-2017/09/15(最終訂正)
|
■ 総論
葉は茎からでて、平らに広がった部分で、通常はそこから芽がない。寿命があり、時が来ると根本から切り放され落葉する。通常扁平で、光合成と蒸散を主な役割とする器官。光を受けやすいように水平に広がる。
秋に落葉するものと越冬するものがある。ふつう緑色であるが 水草のレッド ミリオフィラムのような茶緑色や茶紅色等もある。また、秋から冬の落葉前に紅葉で赤食になるもの(イロハカエデ)や黄葉で黄色になるもの(イチョウ)がある。
また、葉の形やつき方等は、植物の種類を見分けるのに重要な手がかりとなる。
|
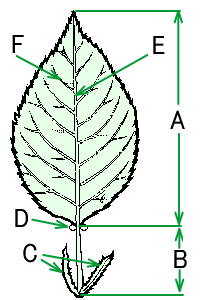 ■ 葉の作り ■ 葉の作り
右図の様に
葉身(ようしん A) 葉柄(ようへい B) 托葉(たくよう C) の3つの部分からなる。
葉身の根元の蜜線(みつせん D)は、身近なものではソメイヨシノがわかりやすい。
葉には、筋が入るのが普通でこれは、茎から葉に入った維管束であり、葉脈(ようみゃくE)と呼ばれる。また中央に走るものを主脈(他に中央脈とか中肋(ちゅうろく))と呼ぷ。主脈の途中で側方へと分かれて広がる枝の脈を側脈(そくみゃく F)と呼ぶ。<<参考写真>>
葉身が深く裂け、葉脈に達すると、葉身はいくつかの部分に分かれてしまう。
このような葉を複葉(ふくよう)と呼ぶ。
右図の様な葉身がひとつの葉を単葉(たんよう)という。 |
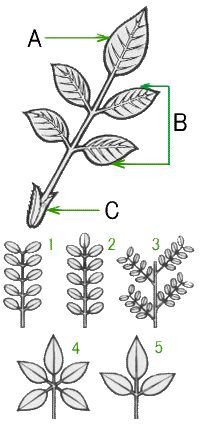
■ 複葉(ふくよう)の作りと種類
先端の物を 頂小葉A。
その他を側小葉B。
付け根は 単葉と同じ托葉 C。
1.偶類羽状複葉 2.奇類羽状複葉 3.2回羽状複葉
4.掌状複葉 5.3出複葉
|
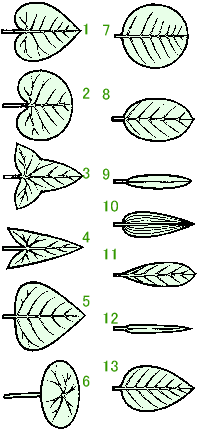
■ 葉の形
1.心臓形
2.腎臓形
3.矛(ほこ)形
4.矢じり形
5.三角形
6.盾(たて)形
7.円形
8.楕円形
9.線形
10.披針形
11.倒披針形
12.針形
13.卵形
他に へら形や舌形など多様な形がある。
■ 葉序 葉のつき方
◇互生葉序 (下図左)
葉が位置をずらして様々な方向に出ている物。単に互生ともいう。この出方が多い。また、実際には互生でありながら、節の間が短くなり対生や輪生のように見える場合は、偽対生・偽輪生ということもある。
◇対生葉序 (下図中央)
葉が茎から出るとき、茎の同じ高さから、向き合うように2枚の葉が出ること。単に対生ともいう。対生のものは少なく種類の同定に重要な手がかりになる。 |
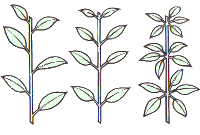 ◇輪生葉序 (下図右) ◇輪生葉序 (下図右)
茎の同じ高さから3枚以上の葉が出るも。単に輪生ともいう。葉の枚数により三輪生、四輪生などということもある。
他に
◇十字対生
対生葉序の一種で、隣りの節から出た葉が互いに直交しているもの。上から見ると葉が十字に出ているようにみえる。
◇二列対生
対生葉序の一種で、平面的に対生していること。
+---補足---+
◇束生(そくせい)
上記のどれの場合でも、枝先に集まってつくものをこう呼ぶ。 |
現在書きかけの項目です。 加筆、参考意見等をお持ちしてます。 |
|

